こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に
さて、鉛筆画中級者の人にとって、構図の選び方は表現の幅を大きく広げる鍵となります。ただ描くだけでなく、どう見せるかを意識した構成によって、作品の印象は格段に向上します。
この記事では、プロも活用する「3分割」「4分割」「黄金分割」「√2分割」「√3分割」という5つの構図テクニックに焦点を当て、それぞれの特徴と使いどころを解説。
構図をマスターすることで、主題(主役や準主役、以下主題)が際立ち、視線誘導や奥行き表現が自然に生まれ、観てくださる人の印象に残る鉛筆画へと進化できます。
あなたの描写力を一段引き上げるための構成術を、今こそ見直してみる必要があるのではないでしょうか?
尚、黄金分割・√2分割・√3分割による、分割状態の単純な比較画像を掲載しておきます。これらの分割線は、上下左右から測ってそれぞれ2つづつあることも記憶しておきましょう。

黒…画面中心線、赤…√3分割線、ピンク…黄金分割線、青…√2分割線
これらの位置を考慮して、モチーフの配置を決めるということです。人物画の場合では、縦向きの制作画面であっても√3分割を使って、画面ど真ん中を使わずに動きを出せるということでもあります。
そして、重要なことは、取り扱う一つの構図で、静物・人物・動物・風景・心象風景などそれぞれに使えるので、さまざまなジャンルで順番に制作できるということなのです。
それでは、早速どうぞ!
3分割構図で主題を際立たせる配置術
-220609-2.png)
鉛筆画中級者の人が、作品に奥行きやバランスを与えたいと考えたとき、最も基本的かつ効果的な構図が「3分割構図」です。
画面を縦横それぞれ3等分し、主題の中心を交点や分割線に配置するこの手法は、自然な視線誘導と安定感をもたらしてくれます。
本章では、構図に悩んだときの出発点として、非常に有効な手法である点について解説しましょう。
この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。
毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。
3分割構図の基本と視線誘導の関係
-220608-1.png)
3分割構図では、画面を縦横それぞれ3つに分けて9つのエリアを作り、4つの交点と6本の分割線が生まれます。また、縦横の2分割線(③④)や2つの対角線(①②)も有効活用しましょう。
主題の中心を、これらの交点や線上に置くことで、観てくださる人の視線を自然とそこに集められるのです。
この配置は、過度な中心配置(ど真ん中の配置)による単調さを回避しつつ、構図全体に心地よい緊張感をもたらしてくれます。
左右いずれかに主題を置く演出効果
主題を中心ではなく、左または右の3分割線上に配置することで、画面上の構成にゆとりのある空間が生まれます。
この空間が、視覚的な「呼吸空間」となり、静けさや広がり、あるいは一方向への動きを暗示できるのです。
たとえば、風に揺れる木や、人物の視線の向きに合わせた配置は、作品に動的な流れを与えることが可能になります。
ここに付け足して補足すると、例えば、3分割の左の線に人物を配置して、その人物を右に向けた横向きにした場合には、人物の視線は未来に向けた視線であることを暗示できるのです。
絵画の世界では、画面の左側は過去を、右側は未来を暗示します。逆に、人物を3分割の右側に配置して、左に向けた視線は、過去を振り返っている作品にすることができるということになります。
尚、次の作品では、3分割構図基本線を使いながら、3個のモチーフで「3角形」を構成する構図を作っています。あなたの考える、3つのモチーフを使って描いてみてはいかがですか?^^
-220609-3.png)


- 黄色の線:3分割構図基本線
- 緑色の線:3分割線
- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線
- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治
※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へつながる部分があると、観てくださる人の画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があります。
空間と対比で深まる印象表現

参考画像です
3分割構図では、主題を1つとした場合には、反対側に空間ができます。この空間には意図的に「何も描かない」ことで、主題を強調する対比表現としても機能します。
また、背景にうっすらと質感を描き込むことで、空間的な奥行きと物語性を同時に高めることもできるのです。
鉛筆の濃淡だけで、静寂や緊張感を演出するには、空間の活用がカギとなります。
3分割構図に適したモチーフ例

参考画像です
日常的な静物(空きビン・果物・本など)や、立ち姿の人物、立木など明確なシルエットを持つモチーフは、3分割構図と非常に相性が良いです。
とくに、片側に重心が寄っている構図は、画面全体にストーリー性を与えるため、作品に深みを持たせることが可能となります。
自然な視線誘導を意識しつつ、緊張感やバランスを取る構成が鍵となるのです。
鉛筆画中級者の人が、より完成度の高い作品を目指すには、この3分割構図の理解と応用は避けて通れません。バランス感覚と空間処理能力を鍛えることで、描写力以上に構成力で魅せる力が養われます。
4分割構図で緊張と安定を両立させる方法
-220608.png)
鉛筆画中級者の人が、次の段階へ進む際に、3分割構図の次に知っておきたいのが「4分割構図」です。
画面を縦横4分割して16の領域を作るこの構図は、シンプルで安定感がありながら、使い方によっては大胆な印象や緊張感を加えることもできます。
本章では、4分割構図が、対比や対称性を強調したい場合に、とくに効果を発揮できる構成である点について解説しましょう。
4分割構図の基礎と意図
4分割構図は、画面を縦横4分割して、16の領域をつくる手法です。
全体に4分割基準線が走ることで、均等なエリア配分が可能になり、安定したバランスが生まれます。
一方で、モチーフをどこに置くかで印象がガラリと変わるため、構成力が問われる構図でもあるのです。
どの構図分割基本線でも、制作画面縦横の2分割線と、2つの対角線は必ず入れて、それらの線も有効活用することによって、画面内の配置を充実できます。
尚、4分割構図は、次の画像の中の⑦を地平線や、遠くの山並みに据えることで、「大地の広がり」を強調した制作ができますし、⑧を地平線にすれば、圧倒的な「空間の広がり」を表現することも可能です。
-220608-2.png)
対称構成で緊張感を生む


- 黄色の線:4分割構図基本線
- 青色の線:「抜け」に使うための線
- ピンク色の線:モチーフで3角と逆3角を構成する線

画面下の両角を暗示するためのモチーフを追加で配置した画像。

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治
中央の縦または横の軸を基準にして左右対称、もしくは上下対称にモチーフを配置すると、静的な安定感の中に独特の緊張感も得られます。
たとえば、真正面を向いた人物や、真上から見た食器などがこの構図に適しているのです。
細密な描写と、構図の釣り合いが作品の完成度を大きく左右します。
非対称構成で空間に動きを与える

参考画像です
4分割構図は均衡を基本としながらも、モチーフをあえて片側のエリアに寄せて配置することで、バランスの崩し方に個性が出せます。
この非対称構成では、空白側にわずかに描き込みを加えることで、空間の動きや視線の動きをコントロールできるのです。
鉛筆画中級者の人にとっては、空間の活用力が試される構図とも言えます。
4分割構図に適したモチーフと演出

参考画像です
真っすぐな形状を持つ建築物や、正面を向いた人物、シンメトリー(左右対称)な構造物などに適しています。
また、テーブルの上に置かれた静物を真上から見下ろす視点も、この構図と相性がよい例です。
明暗や濃淡を左右で対比させると、さらに構成の面白さが際立ちます。
4分割構図は、安定性を保ちつつも、描き手の意図次第で緊張感やリズムを演出できる奥深い構図です。鉛筆画中級者の人が、この構図を使いこなせるようになると、作品の構成力が大きく向上できるでしょう。
まずは、対称構成と非対称構成の両方を試し、それぞれの表現が画面に与える効果を体感してみることが大切です。
黄金分割構図の魅力と自然なバランス感の出し方
-220609-2.png)
鉛筆画中級者の人にとって、「黄金分割構図」は美術史において、長年愛されてきた調和の象徴とも言える存在なので、是非取り組んでほしい構図です。
自然界に多く見られるこの比率は、人の目に最も心地よく映る構成とされ、観てくださる人に違和感を与えずに主題を引き立てる力があります。
本章では、黄金分割構図が、静かに惹きつける作品を目指すなら、ぜひ習得しておきたい構図である点について解説しましょう。
黄金分割とは何か?
-220609.png)
黄金分割は、おおよそ1:1.618という比率で分割された構成を指します。
縦でも横でも、この比率に沿って画面を分け、主題の中心をその交点または比率線上に置くことで、視覚的に心地よい構成が自然と生まれるのです。
とくに意識せずとも、なぜか「まとまって見える」作品には、この比率が隠れていることが多く見られます。
あなたの制作画面を実際に測って、その値÷1.618で得られた値で分割するということです。尚、画面縦横にそれぞれ2つづつ分割線はありますので、有効活用しましょう。また、縦横の2分割線と2つの対角線もお忘れなく。^^
目立たせすぎない主題配置が可能
この構図の最大の利点は、主題を過度に目立たせることなく、それでいて確実に視線を集められる効果がある点です。
たとえば、人物や静物をやや対角線寄りの黄金分割ライン上に配置することで、画面に自然な動きが生まれます。
過剰な演出をせずに魅せたいときに最適です。次の作品も参照してください。
-220609-1.png)



モアイのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治
背景との調和で空間に深みを
主題を、黄金分割の位置に置くだけでなく、背景もこの比率で構成することで、画面全体に調和が生まれます。
空や壁のライン、遠景の構成などを黄金比に沿って設計すると、自然な奥行きや空間の広がりが表現できるのです。
鉛筆の濃淡と線の流れも連動させると、より一層完成度が増します。次の作品も参照してください。


青色線:黄金分割線のみの表示

- 青色線:黄金分割線(上下左右の各2本)
- 黄緑色線:4分割線(縦方向に対して3本、対角線・画面縦の2分割線は4分割構図基本線と重複する)
- ピンク色線:画面の中で視線を囲み、鑑賞者の視線を導く方向を示す線
- 水色線:画面縦横2分割と2つの対角線を表す線

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治
黄金分割構図に適したモチーフ例
木立の中に佇む人物、波打つ海辺の景色、人物が手に花を持つ姿など、自然で流れのある情景に最適です。
また、動きの少ない構図でも、比率の力で静かなリズムが生まれます。
構成に迷ったときに使うと、描写が整いすぎず、柔らかくまとまる効果が期待できるのです。
黄金分割構図は、意図的に使用しても、直感的に取り入れても、視覚的に優れた印象を与えられる特別な構成法となります。
鉛筆画中級者の人が、この比率を意識して描くことで、描写技術だけでなく構図全体の美しさが向上します。
次の作品を参照してください。この作品の注意すべき点は、炎の中心を黄金分割の交点の一つに据えていることです。
-220609-3.png)


- 黄色線:構図基本線(対角線・画面縦の2分割線・画面横の2分割線)
- 青色線:黄金分割線(上下左右の各2本)
- 赤色線:画面縦のサイズ(ACあるいはBD間)の1/10の高さをテーブルの最前面の高さとする
- 緑色線:底線(CD)から上記赤色線は画面縦の高さの1/10でしたが、そのサイズの1.5倍の高さとする

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

まずは簡単なモチーフから始め、制作画面に構図分割基本線を入れて、練習を重ねることが、調和のある画面作りへの近道となります。
√2分割構図で奥行きを感じさせる配置テクニック(白銀比とも呼ぶ)
-220608-1.png)
鉛筆画中級者の人が、作品に奥行きと視覚的変化を加えたい場合には、「√2分割構図」は有効な手段となります。
この構図は、日本画や工芸品の設計などにも使われてきた伝統的な比率であり、紙のA判サイズにもこの比が用いられているのです。
本章では、√2分割構図が、自然でありながら理論的な構成が可能で、構図に強弱を与えつつ、視線の移動もコントロールできる構図であることについて解説します。
√2分割構図とは何か?
-220608.png)
√2(約1:1.414)の比率で縦横を構成する手法となります。
この比率で分割すると、画面内に緩やかな斜めの流れが生まれ、主題と背景の位置関係に変化をつけやすくなれるのです。
遠近感や、動きのある構成を描きたい場面で特に効果を発揮します。
あなたの制作画面を実際に測って、その値÷1.414で得られた値で分割するということです。尚、画面縦横にそれぞれ2つづつ分割線はありますので、有効活用しましょう。また、縦横の2分割線と2つの対角線もお忘れなく。^^
視線の流れをなだらかに導く方法
√2の対角線的な要素を活用して、画面の右下から左上、または左下から右上に向かうような配置を意識すると、観てくださる人の視線を自然と奥へと誘導できます。
このなだらかな視線の動きは、空間に奥行きとストーリー性を持たせるために有効です。
構図内に、複数の視点を作りたいときに重宝できます。次の作品を参照してください。
-220608-1.png)



- ピンク色の線:対角線を使った構成を意識した線
- 黄色線:ロウソクの炎を頂点とした「中空の三角」の構図を示す線

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治
対角線と主題の関係で緊張感を演出
主題を、√2の対角線に沿って配置すると、画面全体にゆるやかな斜線の流れが生まれます。先ほども掲載しましたが、次の画像を参照してください。

この斜線に主題の一部を重ねることで、観てくださる人に視覚的な緊張感と、心地よい安定感を与えることができます。
構図が、静的になりすぎないように調整する役割としても役立ちます。
尚、対角線が通っていることを暗示する意味として、絵画は実際の風景を切り取った一部分にすぎませんので、作品の外の広がりを表現するための手法としても、画面上の4隅からの広がりを暗示することは重要です。
この、4隅の充実が必要になる点の関連記事を、この記事の最終部分に掲載してありますので、興味のある人は参照してください。おそらく、あなたは今まで気にしたこともないような部分なはずです。
√2分割に適したモチーフと場面
斜めの要素を持つ風景や、視線が遠くに抜ける街角、並んだモチーフが奥へ連なる構成などに最適と言えます。
また、椅子や本棚、人物の斜め立ち姿といった、動きのある形にも活かしやすいです。
主題に複雑な動きがある場合でも、√2構図が全体を穏やかに統制してくれます。
鉛筆画中級者の人にとって√2分割構図は、単なる見た目の美しさにとどまらず、奥行きとストーリー性を描写に取り入れるための重要なツールです。
次の作品では、画面上の交点Iを中心とした、モチーフの配置に使っています。
-220608-2.png)

第3回個展出品作品 旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治
遠近感を取り入れた構成や、斜め構図の使い方を練習しながら、この構図特有の自然な流れを体得することが、表現力の幅を広げる第一歩となるでしょう。
√3分割構図で大胆な空間表現を取り入れる方法(白金比とも呼ぶ)
改-220608-1.png)
鉛筆画中級者の人が、さらに構図に工夫を加え、空間の広がりや緊張感を強調したい場合、「√3分割構図」は非常に魅力的な選択肢になります。
この構図は、√3(約1:1.732)の比率で画面を構成するもので、縦長または横長のダイナミックな構成に向いているのです。
本章では、空白や余白を大胆に活用することで、空気感や空間の伸びを強調でき、視覚的に強い印象を与えることができます。
√3分割構図とは何か?
-220609.png)
√3分割構図とは、1:√3の比率で長方形を作り、その内部で対角線や補助線を意識しながら主題を配置する手法です。
縦長の構図では、画面の上下に余白ができ、視線の流れが上下方向に引っ張られます。
これにより、視覚的に“高さ”や“深さ”を意識させることが可能になるのです。
あなたの制作画面を実際に測って、その値÷1.732で得られた値で分割するということです。尚、画面縦横にそれぞれ2つづつ分割線はありますので、有効活用しましょう。また、縦横の2分割線と2つの対角線もお忘れなく。^^
空間を強調する大胆な余白の使い方


- 桃色線:√3構図基本線を意識した基本線
- 黄色線:逆三角形の構図を表す線
√3構図では、主題を小さく画面に配置することで、残りの空間が際立ちます。この余白が空間表現における最大の魅力です。
たとえば、人物を画面下部に置き、上部に広い空を描くといった構成では、静寂や孤独、空気感が強く伝わります。
鉛筆ならではの濃淡表現で空白を引き立たせると、画面に深い印象を残せます。
強調と省略のバランスが構図の決め手
空間を広く取りすぎると、主題が弱くなる危険もあるため、主題の形・明度・配置によって画面の重心をコントロールすることが必要です。
逆に言えば、この構図は省略と強調のバランスを学ぶ最適なフィールドでもあります。
鉛筆画中級者の人が一歩先へ進むには、描くより「描かない」部分の使い方も習得することが求められるのです。
次の作品では、縦向き画面で√3構図を使い、「ど真ん中」ではなく√3構図基本線に則った配置にすることで、画面に動きを出しています。「ど真ん中」の配置は、動きのない画面になってしまうからです。

渚にて 2024 F6 鉛筆画 中山眞治
√3分割に適したモチーフと演出法
モチーフを中心にせず、遠くの人物や構造物、または風景の一部を切り取るような表現に最適です。
たとえば、夜空と人物、壁と窓、地平線と木など、モチーフの存在が空間の広がりを感じさせるように構成すると、√3構図の魅力が最大限に発揮されます。
静と動、広がりと緊張が同居するような構図が理想です。
鉛筆画中級者の人が、√3分割構図を取り入れることで、従来の枠にとらわれない大胆な空間設計が可能になります。
空白に意味を持たせ、構図全体に呼吸を与えるような作品づくりを目指すことで、視覚的にも感情的にも観てくださる人に、深い印象を与えることができるでしょう。
次の作品でも、同じ理由で、縦向き画面で√3構図を使い、「ど真ん中」ではなく√3構図基本線に則った配置にすることで、画面に動きを出しています。

渚にてⅠ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治
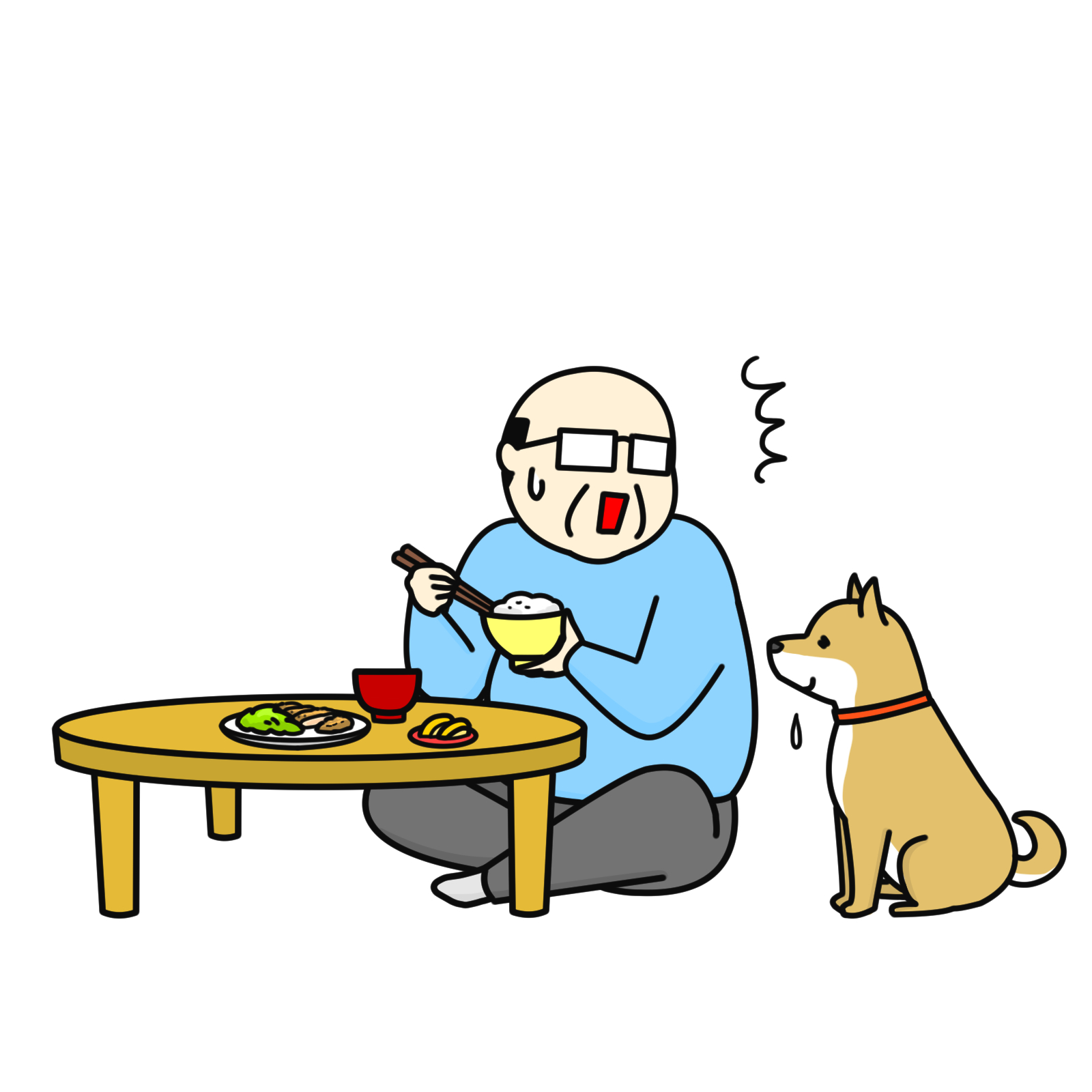
ぜひ一度、余白から生まれる世界を体験してみてください。
練習課題例(構図5選を実践するための内容)

願い 2024 F10 鉛筆画 中山眞治
本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。
3分割構図で静物を描く
空きビンとリンゴをモチーフにし、3分割構図の左または右の縦線上に配置して描く。余白側はあえて何も置かず、空間の使い方を意識する。

参考画像です
黄金分割構図で風景を構成する
一本の木と地平線を用いて、木を黄金分割の交点に配置し、空と大地の比率も黄金分割で構成する。ナチュラルなバランスを体感する。

参考画像です
√3分割構図で空間の広がりを描く
人物を画面右下に配置し、広がる空を鉛筆の濃淡だけで表現する。空白が持つ力と画面全体の印象の変化を意識する。

参考画像です
まとめ:構図で表現力を高めるために知っておきたい5つの分割法

青木繫記念大賞展 奨励賞 2001 F100 鉛筆画 中山眞治
鉛筆画中級者の人にとって、描写力と並んで重要になるのが「構図活用力」です。
どれだけ細密に描かれていても、構図が適切でなければ画面は単調で迫力がなくなり、主題も際立ちません。
この記事でご紹介しました「3分割・4分割・黄金分割・√2分割・√3分割」の5つの構図は、それぞれに異なるバランス感や視線誘導の力を持ち、作品の印象を劇的に変える可能性を秘めています。以下に要点をまとめます。
構図5選のポイントと活用のヒント
- 3分割構図:画面を縦横3分割し、交点や線上に主題の中心を置くことで、自然なバランスと視線誘導が得られる。とくに、静物や人物に向いている。
- 4分割構図:画面を上下左右でそれぞれ4等分することで、対称的な安定感や非対称の緊張感を使い分けられる。建築物や真正面構図に最適。
- 黄金分割構図:1:1.618の比率で分割し、自然界にも多く見られる調和的な構図。人物・風景・静物など幅広く応用可能。
- √2分割構図:1:1.414の比率で分割し、斜め方向に主題を配置することで視線を奥へと導き、画面に奥行きと動的な流れを生み出す。風景や多視点モチーフに効果的。
- √3分割構図:1:1.732の比率で分割し、大胆な空間処理が可能で、空白の力を活かせる構図。孤独感・静けさを表現したいときに有効。
構図はあくまでも画面構成の土台であり、それを活かすためには「どこに、どれだけ、どう描くか」という判断力も欠かせません。
モチーフの選び方や、濃淡の使い方によっても、構図の効果は大きく変化します。まずは意識して構図を使い分けることで、それぞれの特徴と自身の描き方との相性が見えてきます。
鉛筆画中級者の人にとって、構図は単なる形式ではなく、表現の選択肢を広げる「視覚的言語」とも言える存在です。
描写に慣れてきた今だからこそ、構図に目を向け、自身の作品に新たな視点と魅力を加えていく時期ではないでしょうか。
ぜひ今回ご紹介しました5つの構図をもとに、実際に手を動かして感覚をつかんでください。構図を制することが、あなたの鉛筆画の表現をさらに高める確かな一歩となるでしょう。
構図を学んだあとは、実際の練習でどのモチーフを選ぶかも重要になります。モチーフ別に練習内容を整理した練習帳も参考にしてください。
この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。
毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。
ではまた!あなたの未来を応援しています。











まずはこの構図で描くことに慣れ、視線誘導や余白(空間)の効果を体感することが、次の構図技法へのステップとなるでしょう。